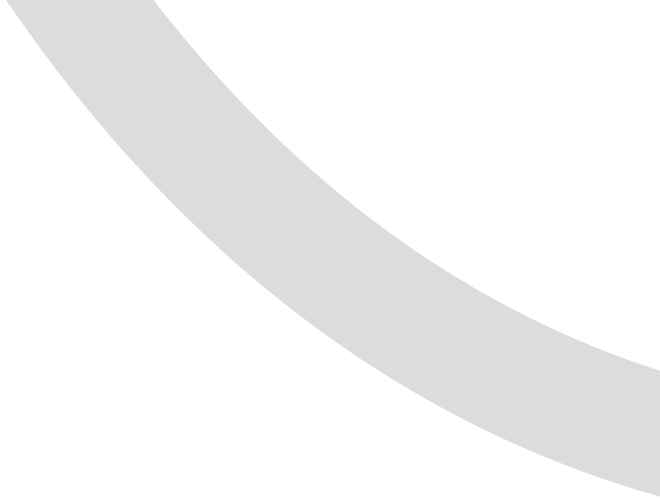
Takahiro Yamaya
山谷昂寛1人目の社員として入社。トップの横で働く厳しさが自己の市場価値を上げる

プロフィール
執行役員/ディレクター
愛知県出身。法政大学を卒業後、大手ITコンサルティング会社に入社。プログラムスキルを持つコンサルタントとして、特にシステムの基本設計から開発にいたる工程を担当。物流会社のDX化に多く携わり、2021年、ネバーマイル代表の深作に誘われる形でネバーマイルに入社。システム構築での業務設計からコーディング、データ分析などを担い、2023年から現職。

会社も自分も初めての挑戦。そこに魅力を感じた
―大手ITコンサルから転職したきっかけを教えてください。
きっかけは、弊社の代表、深作に声をかけてもらったことです。
新卒で入社した会社は数千人のエンジニアやITコンサルタントを抱える大きな会社でした。待遇もよく、数百人規模の大きなプロジェクトにも携われました。しかし一方で、自分の仕事が何に影響しているのかが分かりづらく、「自分の代わりはいくらでもいるよな」という思いがぬぐえませんでした。
自分のやった仕事が、お客さまや会社にどれくらいのインパクトを及ぼしているのかを実感したい、そういう気持ちが徐々に強くなっていきました。とはいえ転職すると決めていたわけではなく、何か別のことをやってみたい、別の組織に行ってみたいというくらいの状態でした。
―山谷さんが望む「実感」がネバーマイルにあると思われたのですか?
明確に認識していたわけではありません。どちらかというと、ネバーマイルという組織に入るというよりは「深作さんと働いてみよう」という感覚で入社を決めました。
当時、深作は会社を立ち上げて2年ほど。1人で仕事をしていてまだ社員を雇った経験がなく、私は転職の経験がない。お互いが初めての挑戦という状況です。そこに未知の領域に踏み込む魅力を感じました。IT人材は市場での需要も高い状況だったので、万が一うまくいかなくても転職先はあるとも考えました。
それに、スタートアップのファウンダーとして事業を大きくしてきた人間の横で働く経験は、めったにできることではない。その経験を解像度高く人に伝えられるくらいのレベルで仕事をしてみたい。その方が、もやもやしたまま前職に留まるよりも価値があると思ったのです。
―未知の領域に踏み込むには勇気が必要ですが、背中を押したのは何だったのでしょうか。
勇気が必要だとは感じていませんでした。深作は前職の先輩で、当時の彼の仕事ぶりを見ていたことが、そう思わせたのかもしれません。
前職でも深作は他の社員とは全く違うことをやっていました。例えば、あるプロジェクトで指揮をとっていたところ、その1〜2年後にはその顧客企業の社長にCIOを任命されました。そんなに短期間で大企業のトップの信頼を得るなんてすごい人だ、どんな行動をしたのだろう、と興味を抱いていました。
深作と話をすると、彼の考えや言葉に「そうだ」と共感することが多いんです。だから一緒に働きたい。シンプルな思いでした。自分が決めたことの責任を自分で引き受けるということには、清々しさを感じます。私がネバーマイルに入社することは、互いの経験やキャリアにとって決してマイナスにはならないだろうと納得できたときが、入社を決めたタイミングでした。
仕事への意識が変化。働くことの意義を実感
―入社して3年以上が経ちましたが、望んでいた「実感」を得ていますか?
はい。今の仕事は、自分のキャリアにとって意味があると感じられるようになりました。
ネバーマイルでのおもな業務は前職と同様で、お客さまの要望を実現するために、業務要件を聞いてシステムに落とし込む、いわゆる基本設計から構築を行うエンジニアです。前職と異なるのは、自分の市場価値がスピード感を持って上がっていると実感できていることです。
例えば日々、経営者とコミュニケーションを取りながら仕事をすることで、嫌でも数字を意識させられます。「自分の行動は経営上でこういう数字になる」「この仕事は会社にとってこれくらいのインパクトがある」と知ることで仕事の重みの感じ方が変わる。時にそれは厳しいものですが、そのキツさに耐えうるだけの働く意義を感じるのです。
それは、ネバーマイルの仕事が市場にとって価値があり、お客さまの助けになっていると胸を張って言えるからだとも思います。
ネバーマイルの価値は、他社だったら長期間を費やすシステム構築のプロジェクトでも、短期間で精度高く、さらに低価格で提供できることです。会社として利益を出すことは前提ですが、お客さまに大きすぎるコストはかけさせない。そうやってお客さまの信頼を勝ち取ることが、今のフェーズの私たちが挑む最大のミッションであり、それをコツコツと具現化できています。
―入社後、ご自身に変化はありましたか?
もっとも変わったのは、仕事に対する姿勢だと思います。責任の重さが増し、当事者意識を強く持つようになりました。プロジェクトに取り組む時の集中力も増しましたし、会議中のアクションなど、日常のちょっとした行動も変化しています。
また、自分の代わりはいないと感じられるようになりました。理由は単純です。例えば今携わっている案件では、1年以上同じお客さまのことを考え続けています。考えている時間の長さが知識の深さにつながります。深い仕事は、すぐに誰かが代われるものではありません。
ただし、この変化が“成長”かというと、そう言い切るにはまだ早い気がしています。今はまだ「いい先生について学んで、自分が変わっている最中」というイメージです。
―「いい先生について学ぶ」というのはどういうことを指していますか?
私にとっての“いい先生”は経営者と仕事をするという経験です。「どうして会社を経営しているのか」「お客さまにどう伝えると、どう見られるか」など、経営者の視座に触れる機会が幾度となくあります。おのずと、どんなモチベーションで働けば、お客さま・会社・自分たちの未来にどんないいことが訪れるのかを理解できるし、自分のモチベーションを向ける先が明確になります。
また、仕事とは、自分で考えてアウトプットしたものをチームなどでレビューしてもらい、お客さまに出せる状態にして、お客さまに説明・納得していただいて成果物を作っていく。簡単にいうとその繰り返しを続けることだと思うのですが、こういった場面で、経営者からのレビューをもらえるのも貴重な経験のひとつです。
今でも「ちゃんと考えられていない」とダメ出しをもらうことがありますよ。入社当初は「言われるから考え直す」という姿勢だったかもしれませんが、今では先手を打って考え抜くことが習慣になりました。“ちゃんとやる”の“ちゃんと”のレベルは、確実に上がっていると実感しています。

組織として固定されたものがない醍醐味
―ネバーマイルはどのような会社ですか?
ミッションやビジョンはありますが、私個人としては「こういった会社だ」と言い切る答えを、まだ持っていません。
創業から4年強を経て会社としてのルールも構築されつつありますが、状況に応じて変化する面も多いです。深作自身も言っていますが「今日は昨日と同じ考えじゃないことが、あるかもしれない」のです。お客さま、市場、未来を見て最速で動くために考えが変化するのは当たり前のことだと思っています。
そういう意味では「組織として固定されたものは、まだない」というのがネバーマイルであり、それがスタートアップの醍醐味なのだと思います。
―そんなネバーマイルに合うのはどのような人物だと思われますか?
変化に一喜一憂しない、落ち着いている人かな。それと、過去の成功体験にとらわれない人がいいと私は思います。年齢に関係なく、自分が得た経験にはみんな自信を持っているものです。ただ、それまでの経験にとらわれすぎると、柔軟性が失われてしまう。
ネバーマイルは誰でもが手を挙げればやりたいことができる環境ですが、基本的な部分はネバーマイルのやり方に合わせてもらわなくてはなりません。もちろん“やり方”をより良くする提案は大歓迎です。しかし、皆で検討した結果、うちには馴染まないということもある。そんな状況を柔軟に受け止めて、臨機応変に考えられる人がネバーマイルに向いていると思います。
それから、粘り強さでしょうか。現メンバーには「根性があるな」と感心する場面が多いです。
―粘り強さは、仕事が長期にわたることが多いから必要なのでしょうか。
もちろんそれもありますが、社内で評価されるか否かという観点でも、粘り強さが重要だと考えます。当たり前のことですが、転職後に短期間で成果を出せることの方が少ない。すぐに評価されるということに重点をおかず、自分がやるべきことに粘り強く取り組み、やりたいことを手に入れて極める。メンバーはそういうタイプが多いです。
個人的にも、仕事のち密さをとても大事にしているので、粘り強さは仲間に求めるポイントの1つです。課題が何百個あろうとも、ひとつずつ丁寧に解決していく。それが成功への最短ルートだと思っていますし、80%を終え、最後の98%までの道のりは特にスピードとち密さを突き詰めることが重要だと考えています。
仕事は厳しいですが、私たちの活動に共感してくれ、一緒に取り組んでくれる仲間の増加を心待ちにしています。





